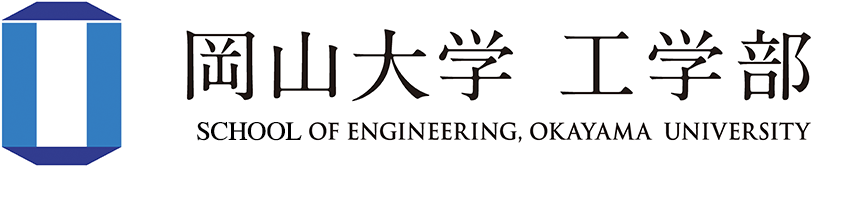テキスト解析プログラム開発に携わった松本さん
工学部卒業生の松本寛生さん(竹内孔一/自然言語処理研究室)(令和5年度年卒)、学術研究院環境生命自然科学学域(工)の竹内孔一准教授、学術研究院社会文化科学学域(経済)の尾関美喜准教授が開発したテキスト解析プログラムについて1月17日に特許を出願しました(特許出願番号2025-006907)。
同研究は、岡山大学 AI・数理データサイエンスセンターサイバーフィジカル情報応用研究推進部門が開催する研究会をきっかけに、工学系竹内准教授と経済学系尾関准教授、および研究当時学部4年生の松本さんが文理融合研究チームを立ち上げてテキスト解析プログラムを開発。既存手法と異なるアプローチであることから、入念な準備期間を経て、特許出願に至りました。
本学では学生の研究活動が実社会への貢献につながる事例が多数あります。今後も、若い研究者たちの挑戦と成果が、社会の発展に寄与することを期待しています。
【本件問い合わせ先】
学術研究院環境生命自然科学学域(工)
准教授 竹内孔一
E-mail:takeuc-k◎okayama-u.ac.jp
※◎を@に置き換えてください
2025(令和7)年4月30日に令和6年度工学部学業成績優秀者への賞状授与式が執り行われました。本賞は当該年度の第1~第3学年の学生の中から、優秀な成績を収めた方に授与されます。(コース毎に授与される人数が定められています。)

(賞状授与の様子)

(真剣な様子で学部長からの激励の言葉を聞く学生)
受賞学生に行ったアンケートでは、以下のような声が寄せられました。
Q.受賞したお気持ちを教えてください。
・学業成績優秀賞という制度を今回初めて知り、驚いたと同時に、自分の中で大きな達成感になった。
・自分の1年間の頑張りを評価してもらえた気がして、とても嬉しかった。
・2年連続で受賞しているので3年生でもこの成績を維持できるように頑張りたい。
・これからの研究も今までと同じように頑張って成果をあげようと思った。
Q.「これを頑張った!」を教えてください。
・全ての授業に出席し、課題に丁寧に取り組むことを心掛けた。
・高校と同じように勉強した。
・一般教育科目にも真剣に取り組んだ。
・予習に時間をかけて、ある程度講義内容を頭に入れてから講義に出席するようにしていた。
・課題はできる限りの満足いくまで頑張った。
・教科書をひたすら理解すること、また、自分の中で疑問点や不明点を一切なくすことを心掛けた。
Q.今後の目標は何ですか?
・文武両道しながら、部活でも学業でもいい成績をとる。
・留学のためにIELTSを頑張る。
・卒業研究をしっかりとこなし、自分の研究者としてのスキルを身に着けたい。
・情報工学に精通した技術者を目指したい。
・土木建築両方のスキルを持った社会人になりたい。
・現在の学びを深めつつ、それが社会でどのように役立つかという視点も意識していきたい。インターンなどの機会があれば、積極的に参加していきたいと思う。
・研究活動においても好奇心を持ち、楽しみながら探求したい。

式の後、工学部1号館の前で 賞状を手に 学部長と記念写真を撮影しました。
2025年4月15日にフランスのCYセルジーパリ大学のAlain Jaillet教授が岡山大学工学部に来訪され、Jaillet教授、高橋規一工学部長、石田衛教授(岡山大学教育推進機構学習・教授支援(CTE)部門長)の三者で懇談を行いました。懇談では、Jaillet教授からはCYセルジーパリ大学の概要とCY Tech(サイテック:工学大学院)で実施しているサマースクールや国際交流活動の内容について紹介があり、高橋工学部長と石田教授からは本学の国際交流活動の内容を紹介しました。また、両国の大学教育や大学と産業界とのつながりについて活発な意見交換を行いました。
-1024x768.jpg)
記念撮影4月15日(左から高橋工学部長、Jaillet教授、石田教授)
環境理工学部の30年の歴史を多くの皆さまと共有するために,この度30周年記念誌を再編集し,30年史を作成いたしました。環境理工学部の同窓生,関係教職員以外の皆さまにもご覧いただくことで,環境理工学部について知っていただく機会になれば幸いです。
詳細は、以下のリンクをご覧ください。(本HP内該当ページへリンクします)
環境マネジメントコース・応用生態学研究室4年生の小見山紗英さんが「第72 回日本生態学会大会ポスター賞優秀賞」を受賞しました。研究内容:人間が生活を送る上では、自然や生態系から様々な恩恵を受けています(生態系サービス)。近年、“文化”や“自然への関心や認識”が、生態系サービスの量や質に影響を与える重要な要因であることが指摘されています。本研究は、都市域や中山間地域に身近な生き物のオンライン検索数の時系列データを解析し、コロナ禍の生活様式の変容と身近な生き物への興味関心の程度の関連を明らかにしました。人間活動と自然環境の関わりを新たな視点から考える、学際性の高い研究です。
研究室のホームページはこちら(外部リンク)
大会名:第72回日本生態学会大会
開催場所:札幌コンベンションセンター
題目:身近な自然への関心とその季節性の変化:オンライン検索数のコロナ禍前後の比較
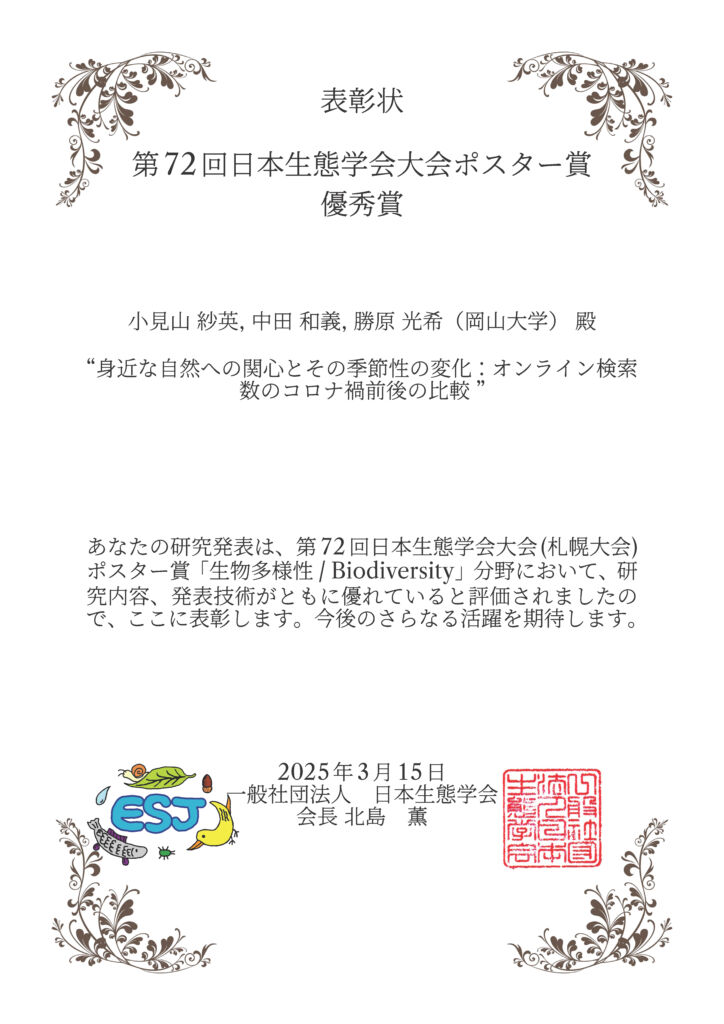
当学部も参加しております第74回国立大学工学部長会議・総会(期間:令和6年5月23日~24日)において採決された要望事項を、当番校である山形大学工学部が代表して文部科学大臣宛てに提出しました。
要望事項は、「多様な人材確保の仕組み作りについて」及び「収容定員による定員管理の問題点及び学部定員管理の緩和措置について」の2項目です。これらは、工学系大学が直面する重要かつ切実な問題であり、現段階で国として検討している事項があればご教示いただくとともに、今後の検討課題としていただくよう要望しました。
要望書の詳細は、以下のリンクをご覧ください。(山形大学工学部Webサイトへリンクします)
11月2日(土)に開催の
2024年岡山大学 工学部・環境理工学部 合同ホームカミングデイ ですが、
大学祭との同日開催の為、駐車場の混雑が予想されます。
ご来場には公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
10月15日(火) 14:00-16:30 工学教育外部評価委員会が本学工学部1号館で開催されました。この委員会では,工学部の教育プログラムの改善・向上を図ることを目的として,学外委員11名をお招きして,意見交換を行いました。令和3年4月の工学部改組後の教育,入試,国際活動,また内部質保証等について,貴重なご意見を数多くいただきました。
【本件問い合わせ先】 学務課工学部担当 井上
ogg8018@adm.okayama-u.ac.jp


環境・社会基盤系環境マネジメントコースは8月26~30日、「OU course in the NTU-UR-OU Exchange Program: Research Experiences in the field of SDGs Field Environmental Science」(以下、岡山大学コース)を開催しました。今回のプログラムには、環境マネジメントコースの2年生6人、3年生1人が参加し、国立台湾大学(NTU)からは学部生8人と引率教員の蔡瑞彬(Tsai Jui-Pin)准教授、スリランカルフナ大学(UR)からは学部生4人と引率教員のDewpura Acharige Lilisiya Leelamanie教授が来学しました。
開講式では、難波徳郎工学部長による開催のあいさつの後、九鬼康彰環境マネジメントコース長によるコース紹介、本学学生による岡山の文化紹介が行われました。参加学生は8講義(講師:前田守弘教授、近森秀高教授、中田和義教授、勝原光希助教、宗村広昭准教授、辻本久美子准教授、哈布尓助教、九鬼康彰教授、森也寸志教授)を聴講し、午後のラボツアーでは、最先端の研究活動に触れました。研究発表会では、講義やラボツアーで学んだことを他のグループや教員に向け紹介しました。また、フィールドトリップでは、児島湾締切堤防耐震工事の現場を訪問し、農林水産省中国四国農政局岡山南土地改良建設事業所の須山次長から、締切堤防耐震化工事の概要説明を受けた後、工事現場を見学しました。さらに、同農政局四国土地改良調査管理事務所の協力を得て、国営かんがい排水事業である香川用水土器川沿岸地区を訪れ、満濃池土地改良区の浅野雅也事務局長、岡田東地域活動組織(あやうた地域広域協定の一構成組織)の籏岡正一代表、株式会社ウエスコの齊藤光男氏から、農業水路における環境配慮工法や水生動物保全、農業用水の運用、世界かんがい施設遺産である満濃池の概要などについて説明を受けました。
また、岡山大学コースに先立ち、8月11~17日には、NTUコースが台北で実施され、岡山大学コースに参加した環境マネジメントコースの7人が参加しました。NTUコースでは、開会式、キャンパスツアーの後、土壌環境における温室効果ガス排出と炭素隔離、流域管理・モデリング・分析、循環経済技術・都市グリーン工学、不飽和土壌水浸透、水資源管理・システム動的モデリング、気候変動の水文スペクトル分析、建築環境における気候変動対策などの講義を受けました。また、象山公園や農業用水路施設を訪問し、座学で学んだことの応用事例を見学しました。
本活動を通して、3大学の学生は環境研究の考え方や他大学の最新研究成果などについて学ぶとともに、他国の学生と英語でコミュニケーションできる楽しみを感じることができた様子でした。また、工学部や環境生命自然科学研究科がこれまで取り組んできた教育研究活動の成果をアピールする機会となったことにより、今後の教員・学生交流や共同研究についても議論を進めることができました。これを契機に、環境マネジメントコースでは、学生および教員の海外交流をより一層活発に進めたいと考えています。
本交流事業は2022年度から毎年実施している双方向プログラムで、JSTさくらサイエンスプランおよび株式会社ウエスコから支援を受けています。本プログラムの詳細はこちらをご覧ください。
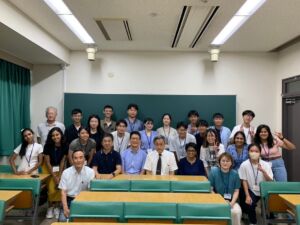
開講式の集合写真(難波学部長、九鬼環境マネジメントコース長、他関係教員と参加学生)

応用生態学研究室のラボツアー水生動物を観察する様子

香川用水で環境配慮型農業用水路を見学する様子

学生による発表会の様子

台湾での土壌調査の様子

象山公園で生態系配慮型施設を見学
【本件問い合わせ先】
学術研究院環境生命自然科学学域 教授 前田守弘
TEL: 086-251-8993